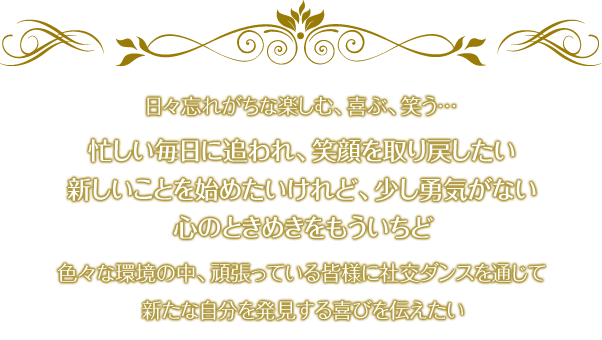






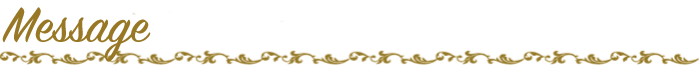


はじめまて。ダンススクール市川の市川学(兄)、市川久(弟)です。
2007年10月、四谷三丁目駅徒歩1分にダンススクール市川を開設致しました。
私達兄弟は10代の頃から社交ダンスを始めましたが、当時、日本国内で子供が社交ダンスを踊れる場などはほとんどなく、趣味としてもあまりポピュラーではありませんでした。
しかし二十歳を過ぎ、初めてイギリスへダンス留学をした時、沢山のジュニアが社交ダンススタジオに通い、大人達と同じように踊っているのを見て、とてもカルチャーショックを受けたのを覚えています。
現在では、社交ダンスが生涯スポーツとして幅広い年齢層の方に親しまれるようになりました。グローバルな世の中になり、人々のつながりがデジタル化される便利な時代になりましが、人と人が手と手を取り合い、デジタルでは感じられないコミュニケーションを取る術を社交ダンスでは大切にしています。そのコミュニケーション力が注目され、最近では学校教育の授業に取り入れられようになりました。
また、ダンスされている多くの方は「ダンスは心と体に良い」と答えます。
心に良いので、気持ちが明るくなり、物ごとに前向きになります。
体に良いので、健康を維持し、自然に姿勢も美しくなります。
いつまでも若々しい心と体で、楽しくハリのある毎日を過ごしませんか…!
ダンススクール市川では、皆さまの忙しい日常から少し解放され、リフレッシュ出来るような空間作りを目指し、お一人お一人に合ったダンスレッスンをご提供いたします。


Wilhelm Gause • Public domain
ボールルームダンス(社交ダンス)の歴史は、中世期のヨーロッパにそのルーツがあるといわれています。
当時、ヨーロッパ各地では、祝い事や祭りに庶民達が集まり、人々の楽しみやコミュニケーションとして踊られた民族舞踊がありました。
そしてこれらのダンスは17世紀に文化・芸術をこよなく愛したフランスのルイ14世の目にとまり、宮廷に取り入れられました。宮廷の舞踏室を「ボールルーム」と呼ぶことから「ボールルームダンス」という名称となり、社交場で踊る「社交ダンス」などと呼ばれるようになりました。
日本では鹿鳴館時代に、上流階級の間で外交政策上の必要性から、欧米をお手本に社交ダンスを導入するようになりました。1918年(大正7年)頃、日本に初めてダンスホールが
開設され、富裕層を中心に社交ダンスが踊られ始めました。
また、一般庶民に社交ダンスが広まったのは、第二次世界大戦後、進駐軍向けに開設されたダンスホールで、若い男女の出会いの場としてダンスパーティーが流行し、ジルバやマンボなどのアメリカンスタイルダンスが流行りました。
近年では、スポーツ性と芸術性を兼ね備えたボールルームダンスは「競技スポーツ」として世界的な広がりを見せています。
競技スポーツとしてのボールルームダンスには、「スタンダード種目」と「ラテン種目」の2つの部門に分かれています。





